《 はじめに 》
2008年11月、筑紫哲也さんが亡くなりました。訃報を知った時、私は最も親しい友人を亡くしたような深い哀しみを憶えました。
私ごときが勝手にこんなことを言うのはおこがましいのですが、筑紫さんはそう思わせてしまうような懐の広い優しさを持ち合わせたジャーナリストでした。
1度接したことのある人なら誰もがそう感じたことでしょう。
実は筑紫さんとは一緒に延べ1ヶ月余りもヨーロッパを旅したことがありました。ロケの合間を見てはよく2人で美術館へとタクシーを飛ばしたものです。
ベルリン国立歌劇場で生まれて初めて生のオペラを聴いたのも筑紫さんとでした。
年が近いとこともありましたが、何よりも親しく接してくれる筑紫さんの人柄が私を行動的にしていたのです。
私たちの目的は当時朝日新聞の日曜版に連載されていた「世界名画の旅」のテレビ番組を制作することでした。残念ながらスポンサーの関係で番組は終了となりましたが、「何とかして続けようよ」と惜しんでくれたのも筑紫さんでした。
それから10数年後、私は久し振りに筑紫さんに会うためにTBSの報道局を訪ねました。少し白髪が増えていましたが、相変わらず少年のように人懐こい優しい笑顔の筑紫さんが待っていました。
その折たまたま、ある企画の話をしたところ「本当にやるの。俺はそう言うのをやりたりたいんだよ」と身を乗り出してきた姿を忘れることが出来ません。
毎日のニュースと言う束縛から解き放たれ、もっと自由に活動したい想いもあったのではないかと思います。
筑紫さんほど文化に造詣深く理解と関心を持ったジャーナリストを私は知りません。不肖ながら今一度筑紫さんとは「文化への自由な旅」をしてみたかったものです。
ところで私は長い間ドキュメンタリーの構成・演出にたずさわってきました。仕事上いろいろなテーマ、いろいろな場所、多くの人達に出会ってきました。筑紫さんとの出逢いもその中の一つでした。
普通取材量は放送時間の6倍から10倍以上にもおよびます。裏を返せば放送される番組の数倍もの情報が捨て去られていることになります。また番組を制作する側の苦闘の姿が知られることも殆どありません。私はそれらのことがずっと心に引っかかっていました。
話は飛躍しますが1997年4月27日の日刊紙の片隅に、次のような記事が掲載されました。
『ゲルニカ爆撃で謝罪へ 独大統領』「25日付の独紙フランクフルター・ルントシャウは、ヘルツォーク大統領が27日に行われるスペイン・バスク地方の町ゲルニカ爆撃60周年式典に書簡を送り、ナチス・ドイツによる空爆を謝罪し、生存者や犠牲者の遺族に和解を請うと報じた。
人民戦線内閣とフランコ将軍派によるスペイン内戦中の1937年4月26日、ナチス・ドイツはフランコ派支援のためゲルニカを空爆し、住民1000人以上が死亡、大半の建物が破壊された。その惨状は、ピカソの大作『ゲルニカ』で全世界に告発された」
というものでした。そしてその記事からわずか3か月後の7月25日の夕刊の死亡欄に、
「ドラ・マールさん(画家・写真家)16日、パリで死去、90歳。パブロ・ピカソの人物画のモデルとして有名で、愛人の一人としても知られる。モデルとなった作品には『ドラ・マールの肖像』などがある。1937年に描かれたピカソの代表作『ゲルニカ』の制作過程を撮影した」
との記事が載りました。何故この小さな見出しの記事が私の目に止まったかといえば、言うまでもなく筑紫さんとスペイン北部の山間にある小さな町ゲルニカを取材したことがあったからです。
その折、私たちはピカソゆかりの地や多くの関係者、特にゲルニカ爆撃時、被爆体験した生き証人に町を案内してもらいながら、貴重な歴史の断片を生々しく聞くことができました。その帰りのロケバスの中でした。
私はこの貴重な体験と情報、そして番組取材の裏話を活字に残しおきたいと思い、筑紫さんにその思いを話し「名前を出しても良いですか」と尋ねました。筑紫さんは「良いよ」一つ返事で快く了解してくれたのでした。
ですがその思いも実現することなく数十年もの歳月が走り去りました。筑紫さんが亡くなってはじめて、その時の会話が昨日のことのように蘇ってきました。
これから記すドキュメントは、私の人生に大きな栄養を与えてくれた筑紫哲也さんへのオマージュであり鎮魂の記録でもあります。
Ⅰ・ピカソ・青の源流を求めて(青の時代)
●南仏の夜・カーニュ・シュルメール
私たちのピカソ『青の時代』と『ゲルニカ』をめぐる旅は、実はゲルニカの町に入る4日前の南仏オード・カーニュ・シュルメールから始まっていた。いや正確にいえば、今回のロケそのもは2週間前から始まっていた。というのもオランダ、パリを中心にゴッホ『オーベールの教会』の取材を終え、続いてルノワールの『町の踊り、田舎の踊り』を撮るためにこのカーニュ・シュルメールに来ていたのである。
カーニュにはルノワールが最晩年を過ごしたアトリエがあった。出演者は中尾彬さん。ここで筑紫さんを迎え「ピカソ」の取材に入る段取りになっていた。
カーニュはニースから車で走って15分足らずの隣町で、美しい紺碧海岸に面した小さな町である。ルノワールが最初にカーニュで過ごしたのは1899年、58才の時であったが、持病のリューマチが再発し、パリの冬の厳しい寒さを避けるために、医者から南仏行きを勧められたからであった。
カーニュが気に入ったルノワールは1903年パリから移って来るが、1907年にレ・コレット荘を手に入れ78才で死ぬまでの12年間をここで暮している。
レ・コレット荘はオリーブの木やアーモンド、ユーカリなど豊かな緑に囲まれた小高い丘の斜面にあり、庭にはルノワール64才の作であるブロンズの裸婦像『勝利のヴィーナ ス』が立っている。館の二階には主にヌードを描いたというアトリエがあり、ルノワールが使っていた車椅子やイーゼル、モデルが横になってポーズをとったというベッドなどが当時の様子を再現するように残されている。
花や果物など静物の小品を描いた小さなアトリエもあり内部は自由に見学することができる。そんなルノワールにまつわる撮影をしながら、私たちは重大な問題を抱え悩んでいた。



オード・カーニュ レ・コレット莊 ルノワール「勝利のヴィーナス像」
●とんだ誤算
東京でのプランでは、ニース空港で筑紫さんを迎えて直ぐ、次のロケ地であるスペイン国境近くのコリューまで車で移動する手筈になっていた。ニースからコリューまでは凡そ500キロ、高速で走っても6時間はかかる事になる。
コリュー到着が夜では宿泊するだけで撮影どころではない。おまけに翌日の午後1時には、ピレネー山脈を越えたスペインのバルセロナにあるピカソ美術館へ入る必要があった。
コリューに拘ったのはピカソが残した重要な絵があるとの情報を得ていたからである。もし撮影出来ないとなれば、ニースまで筑紫さんに来て貰った意味がない。ことの起こりはニース、コリュー間の移動時間の計算違いにあった。東京では僅か3時間位にしかみていなかたのである。
ルノワール最後の撮影が終わってホテルへ戻ると制作さんが素晴らしいアイディアを出してきた。予算は掛かるが車をもう一台用意する。
つまり、撮影スタッフだけ早朝に先発し、後発隊が筑紫さんを拾って後を追う。そうすればピカソの絵と実景だけは撮影することができるという訳である。
実はこのアイディアを可能にする取って置きの人物がいた。その名はイザベル。まだ20才そこそこの生粋のパリジェンヌで、コーディネーターのクロードの友達であり、パリでのロケの間いろいろと手伝ってくれていた。
パリ最後の晩餐の席でのことだった。「イザベルともお別れだね」と私が言うと彼女は一緒に行きたいと泣く真似をした。男ばかりのスタッフの中にあって、彼女はいっも明るい話題の中心だった。
「イザベル、一緒に南仏へ行こう」口火を切ったのは中尾さんだった。イザベルのブルーの瞳が嬉しそうに輝いた。スタッフ全員異存はない。だが問題は余分な費用をどこから弾き出すかだ。頭の痛い制作さんをよそにイザベルの南仏行きはあっさり決ってしまった。イザベルは可愛い顔してレーサー並みの運転技術の持ち主なのだ。
●東洋のにわか賭博師
難問は解決し、後は明日出発するだけになった。全ての仕事から開放されたのが夕方の5時半、外はまだ明るい。そこで折角南仏まで来たのだからと、ホテル前の海岸で泳ぐことにした。泳ぐなんて何年振りのことだろうか。
雲一つない青い空と蒼い海。光がいっぱいに降り注いでいる。栗石を敷き詰めたようなは浜は裸足に気持ち良かった。ほとんど波もない静かな海に入ってみた。冷たいが意外と肌触りが良かった。
空が紅く染まりはじめる頃、寸暇を楽しんだスタッフもホテルに戻って来た。今夜はニース最後の夜であり『ルノワール』の打ち上げとピカソへの旅立ちの晩餐である。なんの料理にしょうかと話し合っているところへクロードが「モナコへ行きましょう」と言い出した。ニースから高速を走って約50分。そう遠い距離でもない。
話は直ぐに決まった。山間の高速道路を走る途中、クロードがモナコ王国を眼下に見下ろせる見晴らし台に寄ってくれた。急勾配の足下に絵はがきに見るような美しい町並みが広がっていた。背後の山には丁度夕陽が赤く染まって沈まんとしている。ロマンティストのイザベルはモナコ側の風景には目もくれず、山の美しい日没だけを眺め続け、私はモナコの街と日没の美しさに見とれ交互に首を振った。
日光いろは坂のように急な坂道を下ってモナコに入る。グレース王妃が自動車事故で死亡したのもこの道である。荒っぽいクロードの運転に冷や冷やしながらモナコに着いたが、モナコには私たちに似合うレストランは見付からなかった。
ポリスに聞くと隣り街に中華レストランがあるという。モナコまで来て中華レストランでもないが、生憎と洋食には飽きていた。結局、モナコ、モンテカルロを越えてイタリヤ国境近くのマントン郊外まで行ってしまった。苦労して捜した割にはなんのことはない、道路沿いに在るごくありふれた中華レストランでお開きとなった。
既に夜の11時半を回っていた。帰路となるとやはりモナコを通らなければならない。モナコを通るとなればカジノが気になる。カジノが在るとなれば素通りという訳にもいかない。これはもう完全にクロードの策略に違いなかった。
走りながらだれ言うとなくカジノに寄ろうということになってしまった。反対する者もなく皆の目が異様に輝いてくる。
早速、宮殿風のグラン・カジノの入り口に立った。ところが私たちの足許を見た警備員が駄目だという。夏場は背広ネクタイ無しでも入れると聞いていたのだが、原因はスタッフの一人が履いていたスニーカーにあった。足許を見て拒否されるとは予想外であった。
諦めるわけにはいかない。クロードの誘いに吊られて、にわか賭博師達は一ランク落とした「ホテルローズ」のカジノへ雪崩込んだ。深夜というのにカジノの中は光輝き、世界の賭博師達で賑わっていた。
早速、私も300フランをチップにチェンジしてスロットルマシーンに取り付いた。ところが何故かコインが入らない。やり方が分からないでは勝負にならない。そこでイザベルを呼んで聞いたら、なんのことはない壊れているだけのことであった。
半信半疑でやっているとこれが意外と出るのだが、どっこい欲が出たところで吸い込まれてしまった。中尾さんも仕事に劣らず真剣だ。
クロードを捜したらルーレットをやっていた。ジャンポールベルモントに似ている彼は中々様になっている。イザベルが付き添っており、ちょっとしたギャングの情婦と言った風情である。
結局みんなはすってしまったが、クロードはなんと500フランを元手に4、800フランをせしめた。日本円で約10万円。わずか1時間のことだから大変な稼ぎというわけだ。
クロードが一杯奢りましょうと言うので手頃な酒場を探したが、明日のこともあり切り上げることにした。この深夜にまたあの急な坂道を猛スピードで走るのかと内心ゾーッとしたが、海岸づたいに走ることになり、おまけに思ったよりも早くホテルに着いたのでホッとした。既に午前1時30分を過ぎていた。こうして南仏での最後の晩餐は終った。
●国境の町・コリューへ
いよいよカーニュを去る時が来た。珍しく空は霞がかかったように曇っている。昨日までのあの抜けるように真っ青な空が嘘のようだ。出発前に一度ニース空港に立ち寄り、日本へ帰る中尾さんを降ろし、更にイザベルが運転する後発隊の車を確保する必要があった。
結局1時間の遅れで、皆と別れて出発したのは10時半を回っていた。カンヌ、マルセイユ、アルル、ペルピニャンを通過する約6時間のドライブである。
乗員は私にカメラマ ン、V・Eさん、運転のクロードの4人。南フランスの海岸線の殆んどを走りきることになる。海岸線に沿った白い道を車は時速120キロで走り続ける。何しろワゴン車に機材とスタッフの私物など300キロ余り積んでいるので速度が出せない。
ちなみに機材はカメラ1台、交換レンズ類、携帯用モニターに波形モニター、プレビュー用モニターとVTR、バッテリーにバッテリー・チャージャー、三脚大、小、ビデオテープ30本余り、照明器具1式、バッテリーライト2台、2波用ワイヤレスマイク、延長ケーブル、その他工具一式などなど。重量にして150Kgから200Kg余り。
だから移動となると技術スタッフはすべての機材を整理し、ジュラルミントランクにつめ込み、着けば着いたで梱包を解き、再び機材の一つ一つを取り出して整備しなければならない。特に国が変われば通関手続きもあり、荷を解いて見せなければならないこともある。移動は本当に厄介だ。
●車は想い出を乗せて
車はエクス・アン・プロヴァンスの葡萄畑の中を西へ向かって走る。日本なら葡萄は樹だが、ヨーロッパでは背丈1メートルにも満たず正に畑である。
エクス・アン・プロヴァンスといえば、セザンヌが愛した町で、アトリエが残っているはずだが、まだ訪ねたことがない。この町からほぼ真南に30キロ下ったところにマルセイユがある。ここでもロケをしたことがあり懐かしいが、あいにくと高速道路を走っているので立ち寄るという訳にもいかない。
マルセイユは古くから栄えたフランス第一の港街で、商工業の中心でありパリに次ぐ第二の都市である。19世紀末から20世紀初頭にかけて青雲の志を抱いた日本の何人もの画家たちがこの港へ着き、汽車を乗り継いでパリへ入った。
マルセイユは『恋は水色』で代表されるポール・モーリアさんが生まれた街である。由紀さおりさん、パリ在住の現代作曲家の吉田進さんと一緒に、生家やマルセイユ音楽院、そして一時勤めたことがあるというマルセイユ中央郵便局などを捜し歩いたものだ。
その時はあいにく天気が悪く、いざ撮影となったら「マフィアが多いので危ない」とコーディネイターはついて来ないし、泊まったホテルは気味悪いほど裏ぶれた感じだったりで、あまり良い印象は残っていない。
車はアビニョンに向かって北上している。距離的にはエクス・アン・プロヴァンスからアルルを通ってモンペリエへ抜けるのが一番近いが、高速道路の方が速いというので、三角の2辺を北へ上ってまた下る迂回路をとっている。
アビニョンは、民謡『アビニョン橋の上で』の曲で日本人にとってもお馴染みの街である。城壁に囲まれた美しい街のそばを流れるローヌ川には、今もアビニョン橋が半分だけ残っている。
ピカソも夏になると何度となくアビニョンへ来ている。1912年にはマルセル・アンベール(愛称エバ)と知り合い一緒に来ているし、1914年にはブラック、ドランと滞在している。
アビニョンから更に北上してオランジュから折り返すように南下を始める。糸杉の並木が目立ってきた。青空に向かってよじれるように延びるゴッホの糸杉の絵が想い出される。ゴッホは1888年から1890年の間アルルに住み300点にものぼる作品を残した。日本の或る保健会社が58億円という異常な値段で落札し話題となった『向日葵』の絵がここで描かれたものである。
ゴッホはアルルで『黄色い家』を借り、ゴーギャンを呼んで恵まれない前衛画家達の共同体を実現しようと夢見るが、ゴーギャンとの確執から耳きり事件を起こし、近くのサン・レミの精神病院に入院した。
ゴーギャンの部屋を向日葵の絵で飾りたいと描いた一枚の絵が58億円とは、生前たった1枚の絵しか売れなかったというゴッホが知ったら、驚きの余り耳どころか首をかっ切って狂い死にしたかも知れない。
金にあかせ値を釣り上げて買い漁る日本人の見識の無さは、恥ずかしい行為と言うべきだが、バブルが崩壊しこうした馬鹿げた話も余り聞かれなくなった。
アルルにも数年前、ビゼーの『アルルの女』をテーマにロケをしたことがあった。指揮者の山田一雄氏とピアニストの花房晴美さんが一緒だった。ビゼーの管弦楽曲『アルルの女』はドーデの戯曲『アルルの女』の付随音楽として1872年に作曲されたものである。
第一、第二組曲共に全曲が実に音色鮮かでドラマチックな構成となっており、私の大好きな組曲の一つでもある。
そのロケの折はドーデの風車小屋、戯曲の舞台として登場する南のカマルグ地方へも行った。ローヌ川に挟まれた三角洲の湿地帯は自然保護地区になっており、ベニヅル、アオサギ、カモを初め野性の牛や馬などの天国である。
ここは短編映画の名作『白い馬』が撮影されたところで、湿地帯を駈ける白い馬の空撮シーンは今でも眼に焼き付いている。私たちも自然保護官の案内で野性の牛や白馬をま近に見る事が出来た。
アルルはローマ時代の闘技場や古代円形劇場跡、プロヴァンス民族博物館、それにゴッホの『跳ね橋』など見るべきものが多い。山田一雄氏とは、ベートベン『運命』、シューベルト『未完成』の取材でウイーンへもご一緒した思い出があるが、残念ながら1991年79才で亡くなられた。ピアニストの花房晴美さんとは、それから数年後コンサートで再会している。
ムソルグスキー『展覧会の絵』のモチーフとなった絵が団伊玖磨氏のロシア取材で見つかったことから、トーク&コンサートが企画され、映像を私が担当することになったのであった。私は若い頃から音楽と絵との結びつきに深い関心を抱いていたので、こういった新しい試みには大賛成であった。
団伊玖磨氏には番組制作面でも何度となくお世話になったが、スタッフを大切にする優しい人だった。2001年5月中国を旅行中、蘇州市の病院で亡くなられている。
人の出会いは巡り巡って思わぬ時にやって来るものである。
●あれがコリューの町だ!
道路も良く快調な走りだ。4時頃になってやっと地中海が見えてきた。予定では既に目的のコリューに着いている筈だが、まだ一つ手前の町ペルピニャンにも届いていない。やがてバルセロナ方面と書いた標識も見えてきた。スペインに近づいたことを示している。
5時、やっとのことで高速道路を下りてペルピニャンの街へ入った。懐かしかった。この町にも数年前、パリから車を飛ばして来たことがあった。ペルピニャンのすぐ郊外にポール・モーリアさんの別荘があり、忙しい合間を縫ってわざわざ私たちを案内してくれたのであった。
別荘といえば私など海岸か山の上などを想像するが、ポール・モーリアさんの別荘は海岸から少し離れた、彼の所有という葡萄畑の中にぽつんと在った。
広い敷地でのペタンク遊び、ポール・モーリア・グランド・オーケストラ専属のピアニストによる即興演奏、ポール・モーリアさんの伴奏で由紀さおりさんが歌ってくれるなど大変楽しい取材であった。
パリからわざわざ呼んでくれていた調理士による料理、この時ご馳走になったロブスターの味は今だに忘れない。
その折、一度も海を見たことがないというポール・モーリアさんの愛犬の『忠義』を連れて近くの海岸まで散歩に出た。今その海岸線近くを走っているはずだが、それらしい場所は見付からない。
車はペルピニャンの街を抜けて郊外の背の高い並木道を抜けて走り続ける。やがて真っ青な空と海の間に白い壁とオレンジ色の屋根が見え始めた。
5時45分、ニースを発って7時間15分の長いドライブの末、やっと目的のコリューの町へ到着した。距離にして東京神戸間といったところだろうか。小さな町は山の傾斜にへばりつくように海へ下っている。国道から急な坂を下って町の中ヘ入って行った。5時を過ぎているとはいえ、まだ太陽はさんさんと輝いている。とにかくホテルを捜し直ぐにでも撮影を始めなければならない。残り2時間の勝負である。



コリューの全景



コリューの港 画家たち ピカソが買いたかった城
●山頂の古城を狙え
撮影目的のホテル・レ・タンプリエは港に近い町のまん中に在った。ホテル前の石造りの細い路が海に向かって下っている。まるで祭りのようにリゾート客で賑わっていた。
ニースは既にバカンスの最盛期の陰りを見せていたのに、ここだけは別天地のように陽光溢れ、活気に満ちている。如何にも南フランスの田舎町といった風情があって、旅情を掻き立てるには十分である。
生憎ホテル・レ・タンプリエは満室で、私たちが泊まるホテルは上の国道に近いところに用意されていた。おまけに2個所に別れており非常に不便だが、文句を言っている暇もなく直ぐさま撮影の準備に入った。急いでホテルの外観からシュートする。
1900年10月の中旬、19才の誕生を迎える直前のピカソは友人のカサヘマスと一緒に、パリへ行く途中この町を通りかかった。
当時は今ほど交通機関はよくなかったわけだから、馬車でピレネー越えをしたのか、それとも船でこの小さな町の港へやって来たのか。
いずれにしても彼等はこの町のホテル・レ・タンブリエに泊まりパリへ向かった。それから数十年後、画家として大成してからもピカソは幾度となくこの町を訪れるようになる。
通りの賑わいの中を港へ出ると、右側には海に面して古城が立ちはだかり、その手前の小さな入り江には大型のボートや、真中に1本の帆柱を立てた特徴のある漁船が数漕繋がれている。
本当に小さな入り江で、弓なりの砂浜に沿って建物が並び、岬には教会を思わせる灯台が建っている。絵葉書のように美しい景色と温暖な気候が多くの画家や観光客を魅了してやまないのも良く分かる。
そもそもコリューは15世紀頃までは地中海に君臨した商業港で、当時ペルピニャンで産出した金銀刺繍のラシャの輸出港として栄えた港町である。港は今ではイワシ、殊にアンチョビーの漁港として使われているにすぎない。
1463年にルイ11世の艦隊に占領されてから城が構築され、その後砦や塔が増築されているが、ホテル前の駐車場になっている広場を除けば殆んど当時のままの面影を保っているという。
ピカソはこの城が気に入り手に入れようとしたが、すでに国有になっていたために果たしていない。そのせいでもないだろうが、ピカソと城の関係は深く、1930年スール県シゾール近くのボワジュールの城を購入、1959年には中部フランスのヴォーヴナルグの城を買い取ってしばしば訪れている。
1973年ムージャンで亡くなって後、この城の庭に埋葬されたほどだからピカソの城にたいする思い入れは相当なものだったようだ。
ところでこの町を愛した画家にピカソの他ブラックなどがおり、マチスも1905年の夏にドランと一緒に初めてこの町を訪れている。日本人がわざわざ訪ねて行くとは思えぬ小さな町だが、翌年、また筑紫さんとマチスの取材で再び訪れることになろうとは夢にも思いもしなかった。
その折には、マチスが泊まった宿を捜して回ったが、通りがかりの町の古老から藤田嗣治が住んでいたという海岸べりの古いアパートを教えられ、予期せぬ発見に驚いたものである。
陽は西の山に傾いて建物の影が長くなっている。一通り町中のカットが撮れたところで、全景を撮ろうと山頂の古城に向かって車を飛ばした。陽が落ちるまで後30分の勝負だ。見当を付けてアタックするがどうしても上に通じない。
結局2、3度迷った挙句、上から下りて来た農家の車をつかまえて聞いたら、登り口は思わぬところにあった。
やっとの思いで頂上に着いた時にはもう陽は西の山に掛からんとしていた。間一発であった。西陽をあび、茜色に染まる雲ひとつない空と海の間に広がるコリューの町と今朝出発したはずのニースの方へ向かって遥か彼方まで延びる海岸線の美しさは、言葉に表わせないほど素晴らしいものだった。
この風景が撮れただけでもコリューへ来たかいがあった。残るはホテルの御主人へのインタビューだ。これは私が聞くより他にない。私たちは急いで町へ下りた。



ホテル・レ・タンブリエ レストラン・内部
●秘蔵!小さな町で見たピカソの絵
ホテル・レ・タンブリエのレストランは夕食時でまだ多くの観光客で混雑していた。ホテルのレストランとはいえ古い建物で、なんのことはない大衆酒場といった感じである。入口から奥まで壁いっぱいに絵の額が掛かっている。
日本でもよく見かけるタレントや俳優のサインに埋まった田舎の食堂の様でもある。この宿に泊まった絵かき達が記念に残していったものだろう。よくよく見たが一枚として心に引っ掛かる絵は無かった。
若いホテルの主人は客の間を忙しく動き回っており撮影は10時過ぎにしてくれという。こちらとしては早く切り上げたいのだが止むを得ず待つことにした。
既に9時を回っているのに外はまだほのかな光が残っている。
考えてみれば着いてから休む間もなく走り廻っていた。暫く休憩にしようと外へ出たら、なんとイザベルが人混みの中を急ぎ足にやって来るではないか。「イザベール!」クロードが駆け寄る。彼女の後から制作さん、更にその後から筑紫さん。「お疲れさん!早かったですね」と驚いて駆け寄ると筑紫さんはいつもの優しい顔で笑っている。
話によると定刻2時にニースに到着、出発まで時間のある中尾さんと一緒に、なんとオー・ド・カーニュの古城を見に行き、4時頃になってペルピニャンに向けて出発したそうである。とすると私たちがたっぷり7時間かかったところを彼等は5時間しかかかっていないことになる。
それもそのはず最高時速180キロで飛ばしたそうだ。フォードエスコート1400CCで180キロは凄い。しかもドライバーは女のイザベルときている。180キロで飛ばしながら片手ハンドルでカセットテープを入れ替えたりしたとか。
「とにかく恐くって恐くって!生きた気がしなかった」とはさもあろう。
かつて私もマルセイユかららパリへの帰路180キロというスピードを味わったことがある。広い平野を走るのでスピードはさほど感じないが、シャーッというタイヤの音が、今にも車が分解してバラバラになってしまうのではないかという恐怖を煽り立て、本当に命が縮む思いがしたことがあった。
涼しい顔して運転するイザベルに対して、恐怖で引きつった顔で祈るようにして乗っている筑紫さん等の様子が目に浮かぶ。
筑紫さんは今日は撮影無しと聞いている筈だ。しかし、インタビューはこれからである。非情だが筑紫さんにやってもらいたくなった。
事情を話すと筑紫さんは嫌な顔ひとつせず快くOKしてくれた。まだこれから先の打ち合わせもしていないのに、いきなりのインタビュー、酷な話である。
ぶっつけ本番でカメラを回しながらレストランの中へ入って行くことした。
筑紫さんは誰が主人かも知らされていない。随分荒っぽいが筑紫さんならこのやり方も通用する。台本に慣らされている役者さんではこうは行かない。
「えーと、ご主人は…何処かな…あの方かな?」私が目で合図する。突然、客達が大声で騒ぎ出した。なんと私が持っていたバッテリーライトに被せていたトレシングペーパーが燃え出したのだ。これではぶっつけ本番も一時ストップせざるを得ない。
筑紫さんがやっと主人を捕まえた。ところが生憎く英語が通じないとあって急遽クロードが通訳することに。
「ピカソの絵があるというので拝見したくてお伺いしたのですが」
「ご存知と思いますが、4年前に11枚あったピカソのスケッチのうち数枚が盗まれました」
私は一瞬ドキッとした。そんな話は全く聞いていなかったからだ。
ひょっとしたら体の良い断りかと思ったが、ご主人は淡々と言葉を続けた。
「残っているのを全部お見せしましょう」と言ってホテルの古いサイン帳を取り出した。そこには1953年の日付けとピカソのサインがあり、牛の顔が描かれていた。1953年と言えばピカソが72才の頃で、8月にペルピニャンに滞在しているので恐らくその時立ち寄ったのだろう。
年表を調べてみると1954年の夏にも、コリュー、ペルピニアンに旅をしている。7人目の女シルヴェットと出会ったのがこの年の春である。1955年にはカンヌの新しい別荘『ラ・カリフォルニー』に移っているので、コリューはそう遠い距離ではない。
1958年まで毎年のように来ていたらしく、その都度簡単なスケッチを残していた。既に世界的な名声を得ている時であり、巨匠にしては随分気前よく描き残したものである。
次に出されたのは1956年のもので、ハガキ大にカタルーニヤ人が帽子を被り、フォーブルというカタルーニヤ独特の笛を吹いている胸から上の姿を描いたものであった。
ご主人の話によるとピカソはカタルーニヤに憧れていることを示す証拠として描いたそうである。
額入りのもう1枚には色鉛筆で、海のまん中に円い太陽、その左にスペイン、右にフランスを色で表現、その下に葡萄など2つの国に共通した産物が描いてある。
この絵がピレネー山脈を堺にカタルーニヤを表現しているものだということは私にも分かる。右下の隅には『我が友プース君へ』とサインがあった。
その他ピカソが終生こだわり続けたハトとオリーブ、1962年に描いたという闘牛の簡単なスケッチなどを見せてくれたが、圧巻はピカソがカンヌに住んでいた頃に描いたというスケッチブックであった。
スケッチブックそのものはごくありふれた物だったが、開くと中にはピカソらしい力強いタッチで、溢れるばかりにアトリエや人物などがスケッチされていた。
大作の油絵にはない、アトリエで構想を練るピカソの日常の姿をありありと感じさせるものである。「大作は良く知っているんだけど、こうしてあっさりと描いているものには温かみというか実感がありますね」と筑紫さんは感歎の声を上げながら見入った。
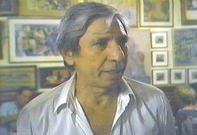


息子のジョジョ.プースさん(53才) 父親のルネ.プースさん(84才) 若い頃のルネさんとピカソ



カタルーニャのスケッチ ピカソのスケッチブック
●ピカソ秘話を知る生証人
インタビューを続けているとひょっこり一人の老人が入り込んで来た。黒いスーツにネクタイをきちんと締めたかっぷくの良い人物である。なんとご主人の父親であるルネ・プースさんであった。当人のプースさんがご存命とは知らなかったのである。
既に84才の高齢でインタビューは無理と若主人が判断していたようだが、私たちが訪ねたことを知ったプースさんが無理をおして自分から顔を出してくれたのだった。直接体験者に会い実話を聞く、これこそ得難いドキュメントである。私たちは嬉しくなってインタビューを続けた。
「ピカソとはお知り合いだったと聞いているんですが、どんな切っ掛けからだったのでしょうか」
「ピカソが最初にコリューに来た時からです。ピカソはその頃カンヌに住んでいたのですが、私はピカソの誕生日には毎回必ず彼の家へ御祝に行っていました。大変優しい人で、コリューへ来た時など皆がサインを頼むと気さくに絵なども描いていました。
或る時は一人の女性が数枚の木の扇子を持って来て、先生絵を描いて下さいと言ったら、一枚一枚に牛の絵を描いてあげるくらいとても親切な人でした」
「ピカソがコリューの町へ何度も来たというのは何故なのか。若い頃の思い出があったからなのか、お聞きになっていませんか」
「私の記憶では1909、10年頃にコリューへ来たことがあって、それを思い出してまた来るようになったのではないかと思います。何故ならコリューの光が好きだったからです」
「記録によると1900年にピカソは初めてフランスへ行ったことになっており、その時に初めてここを通ったという説があるんですが」
「私は1902年に生まれているので、その頃のことは分かりませんがそうかも知れません」
「ところでこのスケッチブックはプースさんの為に、わざわざ描かれたような気がするんですがどうですか」
「おっしゃる通りピカソが私の為に描いてくれたものです。私が毎年ピカソの誕生日に行っていた頃はピカソはまだ貧しくて、部屋には古いテーブルや椅子しかなかったように想います。
そんな折、いつか君の為に私の絵を描いてやると約束してくれました。
そしてその後約束どおりこのスケッチブックを持って来てくれたのです」
ピカソの誠実な人柄を示すエピソードは感動的だった。
しかし良く考えてみると、プースさんがしばしば訪ねたのがカンヌだとすれば、1955年以降の筈で、ピカソは74才頃、すでに裕福であったはずである。画家のアトリエというのは何もピカソに限らず雑然としているのが相場だから、プースさんには貧しく見えたのかもしれない。
仮に思い違いであったとしてもプースさんの話の信憑性を損なうことにはならない。
「長くお付き合いになっていてピカソはどんな人でしたか」
「とにかく優しくて親切な人でした。ひとつのエピソードを覚えています。
実は35年以上も前からパリのサロンにコリュー賞というのが有り、その表彰の為にパリへ行った時のことです。
友人を連れてピカソに会いに行ったら、彼は詩人のアラゴンと打ち合わせをしていたのに、ドアへ出た息子さんが『お父さんルネが来たよ』と言ったら、ピカソはアラゴンに『友達が来たからもう仕事は止めよう』と言って仕事を打ち切って会ってくれました。
そして私の住まいをお見せしましょうと言って、まず1階に連れていって床に立て掛けてあった絵を一枚一枚見せてくれて、次に2階へ上がって寝室まで見せてくれました。それほど親切な人でした」
アラゴンとは左翼作家で詩人のルイ・アラゴン(1897~1982年)のことと思われる。世界人名事典によると、「アラゴンは超現実主義から社会主義的超現実主義に転 向、常に時代の機転を敏感につかんでいった芸術家の典型」とある。第2次世界大戦後、ドイツ軍の占領からパリが解放された直後にフランス共産党に入党したピカソとは深い交流があった。
筑紫さんは隣りにいた若主人(53才)に聞いた。
「息子さんも小さい頃ピカソをご覧になっていると思うんですが、何か思い出はありますか」
「そりゃァありますよ。だってピカソはとても素晴らしい人でしたから。皆が彼のことを知りたがっていました。日常の生活から食べ物まで。彼がやることはすべてが偉大でしたからね」
「バルセロナからフランスへやって来る人達は必ずここを通ったんですか」
父親のプースさんが答えた。
「そうですよ。フランスへ入るにはここの山を通らないと来れませんからね。海沿いの唯一の道ですから」
「海沿いというのは船で来るんですか、それともピレネー山の一番低いところを来るんですか」
「どちらも多かったですよ」
「山道から来た場合はどうやって来たんですか、歩いてとか…」
「歩いた人もいたし、馬車で来た人も結構多かったですよ」
「ピカソについてその他どんな思い出がありますか」
「ひとつ良い思い出があるんですが、残念ながらそのことについてはお話し出来ません。それはピカソのプライベートなことなので。お分かりになると思いますがピカソという人はとても生活をエンジョイする人で、女の人が好きでしたから。私はピカソのような人を愛しているのでこれ以上のことは話せません」
ピカソは1953年の8月にはペルピニアンに滞在し、マドゥーラ陶房の夫人の従妹にあたる若いジャックリーヌ・ロックと出会っており、コリューにも立ち寄り闘牛を観戦したりしている。
また翌年の1954年の春には20才のシルビエット・ダヴィッドと知り合い、その夏にもコリューに旅をしているので、2人の内のどちらかをさすのかも知れない。
ピカソの女性遍歴は良く知られているところだが、プースさんの含みのある発言の奥には、いまだ表に出ていない一時的なつき合いの女性が隠されているのような気もする。本人が口を閉ざすからには、残念だがこれ以上突っ込んで聞くわけにもいかない。
店の片隅で立ったままのインタビューは1時間余りも続いた。通訳を挟んでのインタビューは撮る方も撮られる方も非常に疲れるものだが、コリューでの成果は命がけで車を飛ばして来たのに十分すぎるほどのものであった。
恐らく日本のピカソ研究家でも、この隠れたピカソの作品を手に取って見た人は数少ないのではないだろうか。
ピカソの絵を撮って全てをアップしたのが11時。そう言えばまだ食事もしていなかった。そのまま店先で夕食を済ませ、宿泊先のホテルへ移動、ベッドへ倒れたのは既に午前0時を回ってからであった。
明日は朝7時にはホテルを出発。ピレネー山脈の国境を越えてスペイン・バルセロナのピカソ美術館に午後1時までに入らなければならない。撮影が許可されているのは午後2時から4時までの間に限られている。
もし間に合わなければテーマとなっている絵が撮れず企画そのものが危くなってしまうのだ。